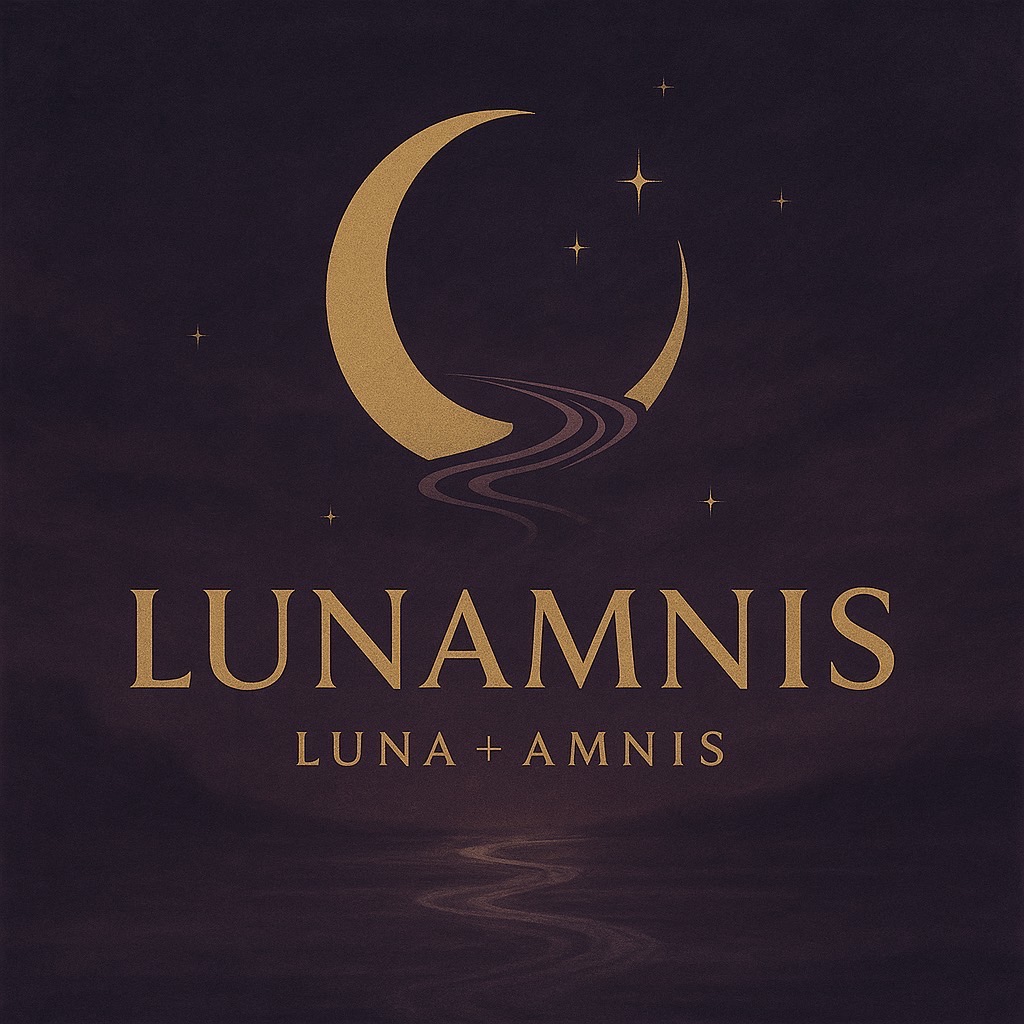「わからないままでいる」力
わからなさは、弱さではない
多くの場面で、私たちは「正解」を求めます。
でも、人生や人間関係、そして自分自身については、簡単に答えが出ない問いばかりです。
そんなときに必要なのが、「わからない」という状態を耐える力。
それは、無知を放置することではなく、不確実性を受け入れる姿勢でもあります。
結論を急がず、問いを抱え続ける
哲学は、すぐに答えを出すことよりも、問い続けることを重んじます。
「なぜ生きるのか」「自分とは何か」など、決して一度で明確にできない問いに対して、
あえて答えを保留し、“わからなさ”にとどまることが、深い思考を育てます。
わからなさが感性を開く
わからないものに向き合う時間は、不安で居心地が悪いかもしれません。
でも、その中でこそ新しい視点や感性が芽生えます。
“わからない”を楽しむ思考力も、
そんな開かれた状態から生まれる発見を促します。
曖昧さを恐れない力を養う
「曖昧なままでいる勇気」は、現代において特に価値のある力です。
AIや即答が求められる時代だからこそ、自分の中で「まだわからない」を大切にし、
そこから世界や他者、自分自身との関係を丁寧に紡ぎなおすことが必要です。
まとめ
「わからないままでいる」というのは、逃げではなく思考の強さです。
すぐに答えを出さなくてもよい。
その余白にこそ、自分だけの問いが生まれ、思考が深まります。
日常の中にある「わからない」を、問いとして抱える習慣を大切にしましょう。