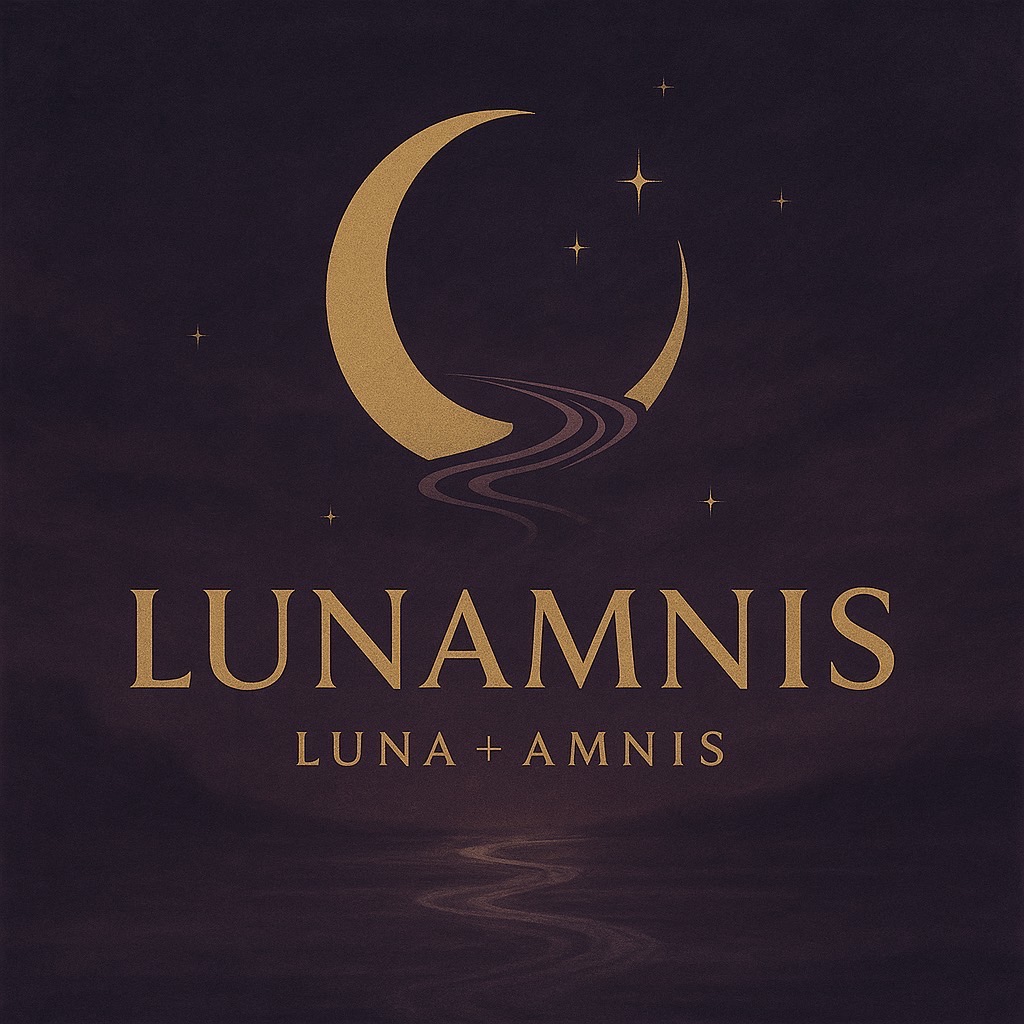“誰のために”働くかを再定義する
忙しい日々のなか、ふと「自分は誰のために働いているのだろう?」と立ち止まる瞬間。
この問いは、働き方の軸を見直す鍵になります。
「収入のため」だけでは片付けられない働く目的について、あらためて考えてみませんか。
① “誰かのため”に働く構図の背景
家族、職場の上司、顧客、社会……
働く目的は、気づかないうちに他者の期待やニーズに基づいたものになりがちです。
もちろん、それ自体が悪いわけではありません。
ただし、自分の意志と切り離されると「やらされている」と感じてしまいます。
→ “やらされている”感覚を問い直す
② 「自分のため」の定義を見直す
「自分のために働く」とは、自分勝手に振る舞うことではありません。
自分の大切にしたい価値観に沿って行動すること。
たとえば「創造する喜びを感じたい」「人の役に立つ実感がほしい」など、
他者とのつながりを含んだ“自分の軸”を見つけることが大切です。
③ 誰の笑顔が浮かぶか?
働いているときに「誰の顔が思い浮かぶか」を問いかけてみてください。
それは家族かもしれないし、サービスの利用者かもしれません。
その人たちが喜ぶ姿を思い描けるかどうかは、仕事のエネルギー源になります。
→ 仕事に“喜び”を感じた瞬間を探す
④ 「本当に応援したい相手」は誰か?
自分が「力になりたい」「届けたい」と思う相手は誰なのか。
たとえば「過去の自分のように悩んでいる人」や「身近な人を支える存在」など、
感情が動く対象に目を向けると、
働くことが“与える喜び”へと変わっていきます。
⑤ 目的は、変わってもいい
キャリアの途中で「誰のために働くか」は変わっていくもの。
それを柔軟に受け入れながら、自分自身をアップデートしていくことが、
長く働き続けるうえでのしなやかさになります。
→ キャリアの軸をととのえる
⑥ “目的”があると働き方が変わる
「誰のために働くか」が定まると、行動の迷いが減り、判断基準がクリアになります。
時間の使い方、働く場所、やるべきことの優先順位まで、自然と整っていきます。
→ 時間の切り出し方と継続術