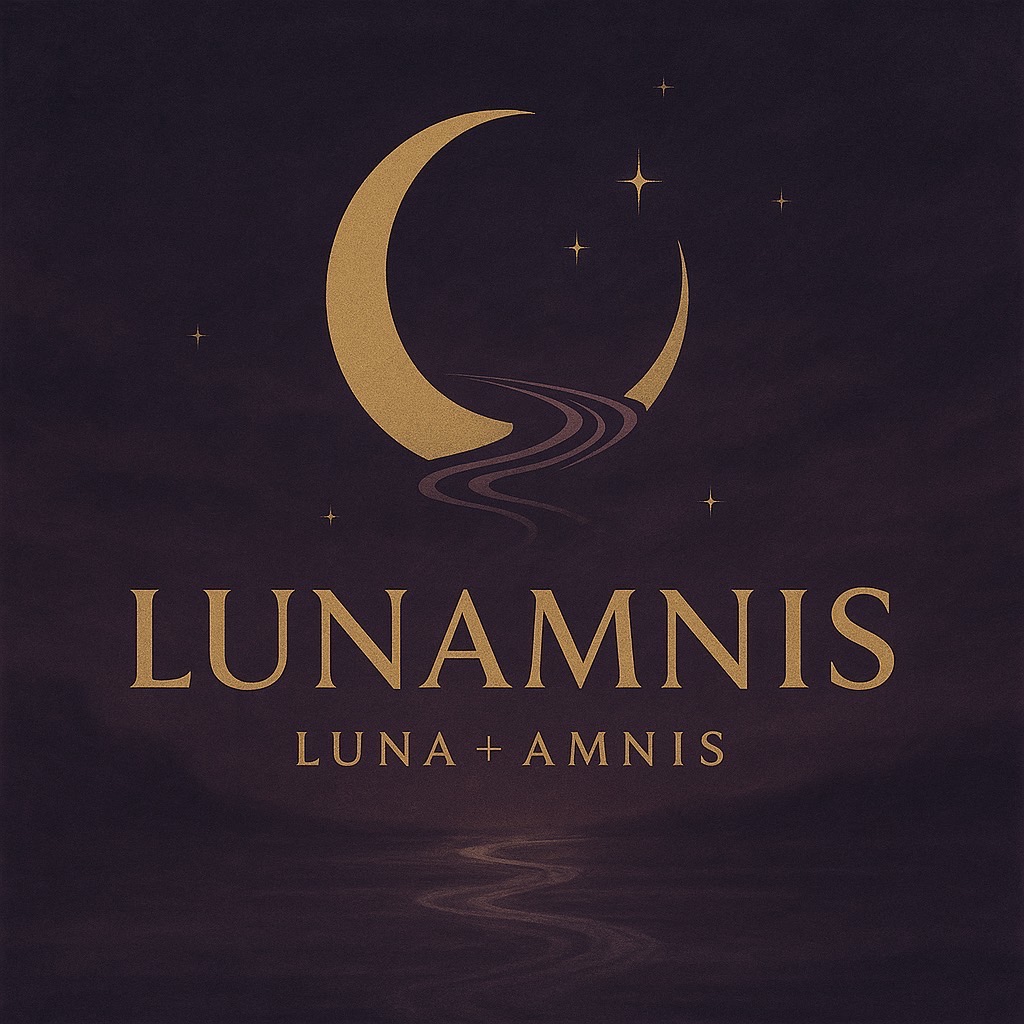“わからない”を楽しむ思考力|不確実さと遊ぶ学びの姿勢
「わからない」は怖くない
知らないこと、不確かなものに直面したとき、
多くの人が「早く理解したい」「答えを知りたい」と思います。
しかし、“わからない”状態をあえて楽しむことは、思考力を育てる最良の方法なのです。
「正解」から離れてみる
学校教育では、正解を出すことが重視されがちです。
けれど、現実世界には「正解のない問い」こそが多く存在します。
そんな問いと出会ったときに頼れるのは、自分の思考です。
不確実なことに“好奇心”を持つ
「なぜわからないのか?」「なぜ気になるのか?」と問い直すことで、
思考が自然に深まっていきます。
「問い」だけを集めるノートを作るのも、思考力を磨く手段のひとつです。
“結論を急がない”訓練をする
すぐに答えを出すのではなく、未整理な思考のままにしておくこと。
それは、思考を整理する習慣ともつながり、心の柔軟さを育てます。
答えの出ない思考も、立派な「学び」なのです。
一冊の本を“わからないまま読む”
難解な本を“味わう”読み方では、あえて「理解しないまま読む」ことを提案しました。
この読み方は、まさに“わからない”と遊ぶ感覚と一致します。
自分の感性にゆだねて、言葉と響き合う読書体験も面白いものです。
問いが残ることに意味がある
一つの問いが解けないまま心に残ると、それはあなたの「思考の火種」となります。
それが思わぬタイミングでひらめきを生んだり、新しい興味を連れてきたりします。
問いの余白を、あえて残しておきましょう。
まとめ|“わからない”は成長の入り口
わからないものに出会ったとき、それを避けるのではなく味わってみる。
それだけで、あなたの学びは一段深まります。
不確実性を歓迎すること。それが、現代における思考力の核心です。